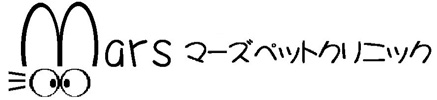2025.08.01 犬の咳から見る心臓病のサイン|呼吸の異変と循環器疾患の関係
「最近、愛犬がよく咳をする」「風邪かと思っていたけれど、なかなか治らない」そんなふうに感じたことはありませんか?
犬の咳には、一時的なものもありますが、中には心臓の病気が隠れていることもあります。特に心臓病に起因する咳は進行性であることが多く、放っておくと命に関わることもあるため注意が必要です。
今回は、心臓病が原因で起こる咳の特徴や、早期発見の重要性などをご紹介します。

■目次
1.原因と種類
2.循環器疾患を示唆する警告サインと緊急性
3.一般的な検査と治療方法と予防
4.まとめ
原因と種類
咳は、異物の侵入を防ぐために起こる体の防御反応で、空気の通り道(気道)に刺激が加わることで発生します。一時的な咳であれば、冷たい空気を吸ったり、食べ物や水が気管に入ったりしたときにも見られます。
しかし、咳が何日も続いたり、明らかに頻度が増えていたりする場合は、何らかの病気が隠れている可能性があります。
咳の原因には、大きく分けて以下の2つがあります。
<循環器疾患による咳>
・僧帽弁閉鎖不全症:心臓の弁がうまく閉じず、血液が逆流することで心臓に負担がかかります。
・肥大型心筋症:非常にまれなケースですが、心筋が厚くなり、心臓のポンプ機能が低下します。
これらの病気は、初期の段階では咳が目立たないこともありますが、病気が進行すると心臓のサイズが大きくなり、気管を圧迫することで「乾いた咳」が出るようになります。
また、心臓のポンプ機能が弱まると、血液が肺に滞留しやすくなり、肺に水分が染み出す「肺水腫」を引き起こすことがあります。肺水腫になると、「痰が絡んだような湿った咳」が出るのが特徴です。
<非循環器疾患による咳>
・ケンネルコフ(感染性気管支炎):ウイルスや細菌による呼吸器感染症です。
・気管虚脱:主に小型犬に見られ、気管が潰れてしまうことで咳が出ます。
・肺炎:細菌やウイルスの感染、誤嚥などが原因で肺に炎症が起こります。
・喘息(アレルギー性気管支炎):アレルギー反応により、気道が狭くなって咳や喘鳴(ゼーゼー音)が出ます。
これらは主に呼吸器系の病気であり、治療方法や予後は心臓病とは異なります。そのため、正確な診断には、検査を通じて原因を明らかにする必要があります。
なお、「逆くしゃみ」と呼ばれる現象も咳と間違われやすいですが、これは病気ではなく、一時的に喉の奥が刺激されて起こる生理的な反応です。心臓病による咳とは異なるため、症状の見分けには獣医師の判断が重要です。
循環器疾患を示唆する警告サインと緊急性
咳に加えて以下のような症状が見られる場合は、循環器疾患の警告サインかもしれません。
<運動不耐性(すぐに疲れる)>
散歩や遊びを嫌がるようになる、少しの運動で疲れてしまう、途中で座り込むなどの様子が見られた場合、心臓が全身に十分な血液を送れていない可能性があります。
<呼吸困難>
肺水腫が進行すると、酸素を取り込む能力が低下し、呼吸が速く浅くなったり、口を開けて苦しそうに呼吸したりすることがあります。眠っているときに咳が出る場合も注意が必要です。
<失神>
突然意識を失って倒れるような症状は、心臓のポンプ機能が低下して脳への酸素供給が不十分になっている可能性があり、重篤な心疾患に関連していることがあります。
<腹部膨満>
心臓のポンプ機能が低下すると、お腹の内臓にも血液がたまります。それにより、肺の時と同様にお腹の中に水分が染み出て、腹部が膨らみます。
これらの症状は、心臓病がある程度進行してから現れることが多いです。特に呼吸困難を伴っている場合は、緊急性が非常に高いため、すぐに動物病院を受診してください。
一般的な検査と治療方法と予防
咳の原因が循環器疾患によるものか、それ以外の疾患かを見極めるために、以下のような検査を行います。
<循環器疾患が疑われる場合の対応>
・聴診(心音・肺音の確認)
・血液検査
・画像検査(レントゲン・心エコーなど)
・心電図検査
・血圧測定
これらの検査で心臓病と診断された場合、基本的には以下のような薬物療法を中心に行います。
・強心薬
・血管拡張薬
・利尿薬
・気管支拡張薬
また、呼吸が苦しい状態であれば酸素吸入を行い、犬の呼吸状態を安定させます。
心臓病は進行性であることが多いため、症状が出る前の定期的な検査がとても大切です。特に7歳以上の中高齢犬では、循環器系の健診を定期的に受けていただくことをおすすめします。
<非循環器疾患が原因の場合の対応>
・身体検査
・血液検査
・胸部レントゲン検査
診断結果に応じて、以下のような治療を行います。
<僧帽弁閉鎖不全症の場合>
血管拡張薬や利尿薬、強心薬などを用いて心臓への負担を軽減し、症状の進行を抑える治療を行います。状態によっては継続的な投薬が必要になります。
<肥大型心筋症の場合>
心臓の収縮やリズムを整える薬、血栓予防の薬などを組み合わせて治療します。根本的な完治は難しいため、定期的な検査と継続的な内服管理が重要です。
<ケンネルコフの場合>
咳止めや気管支拡張薬、去痰薬、抗生剤の投与などの対症療法を行います。安静に過ごすことも大切です。
<気管虚脱の場合>
気管支拡張薬の使用や体重管理が基本となり、必要に応じて外科的治療を検討することもあります。
<肺炎の場合>
原因が細菌性であれば抗生剤、ウイルス性であれば支持療法(点滴や酸素投与など)を行います。必要に応じて入院による集中的な管理が求められることもあります。
<喘息(アレルギー性気管支炎)の場合>
気道の炎症を抑えるために、ステロイド薬や気管支拡張薬を用います。アレルゲンの特定と環境管理も、再発防止に重要な役割を果たします。
また、ケンネルコフなどの感染症予防には、定期的な予防接種が有効です。
咳の原因によって治療内容は大きく変わるため、自己判断せず、必ず獣医師に相談しましょう。
まとめ
咳は一見、軽い症状に見えるかもしれませんが、その背景には命に関わる心臓病が隠れている可能性もあります。「咳が続いている」「いつもと様子が違う」そんなときは、できるだけ早めに受診することが大切です。
愛犬の異変に気づいた際は、どうぞお気軽にご相談ください。
■関連する記事はこちらから
犬や猫の呼吸がおかしい|循環器疾患との関係と早期発見の重要性
★こちらの情報が参考になった方は、星マークをタップしてご評価ください★
犬、猫、エキゾチックアニマル(ウサギ、フェレット、ハムスター、モルモットなどの四つ足で毛の生えた小型哺乳類)の診察は、『マーズペットクリニック』
神奈川県鎌倉市にある動物病院
TEL:0467-39-3882