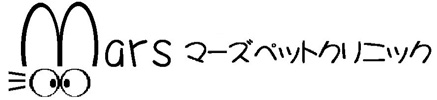2025.06.19 猫の運動不足のサイン5選|室内飼いでも健康を保つ方法
「最近、猫がよく寝てばかりいる気がする」「おもちゃに反応しなくなってきた」と感じたことはありませんか?
近年、猫を完全室内飼いにする家庭が増え、交通事故や感染症のリスクが減少したことにより、平均寿命は延びています。一方、室内の限られたスペースで生活することで、猫の運動量が不足しやすくなっているのも事実です。運動不足は、肥満をはじめ、関節への負担やストレスの蓄積といったさまざまな健康リスクを引き起こす原因になります。
そこで、今回は猫の運動不足によるサインについて、そこから生じる病気のリスクや飼い主様が今日から取り組める室内での運動促進方法などを解説します。

■目次
1.猫の運動不足のサインと健康リスク
2.運動不足から生じる疾患
3.室内での猫の運動促進アイデア
4.年齢・体型別の運動不足対策
5.まとめ
猫の運動不足のサインと健康リスク
以下のような変化が見られる場合は、運動不足に陥っている可能性があります。
<肥満体型>
私たち人間と同じように、猫も運動不足になると肥満になります。肥満になると心臓や関節、呼吸器への負担が増し、病気のリスクが高まります。
<過度なグルーミング>
体の一部分をしつこく舐め続けている場合、運動不足によってストレスが溜まっている可能性があります。運動でエネルギーが発散できないと、不安や退屈感から過剰に毛づくろいをするようになり、皮膚が赤くなったり、脱毛が見られたりすることもあります。
<問題行動やいたずらの増加>
急に家具を引っ掻いたり、トイレ以外の場所で排泄したりする行動が増えてきた場合も、ストレスのサインかもしれません。適度に体を動かす時間がないと、精神的に不安定になり、問題行動として現れることがあります。
<無気力>
猫がおもちゃに興味を示さなくなったり、日中ほとんど動かずに寝たりしている状態も、運動不足の可能性があります。筋力の低下により体が重く感じられ、動くことそのものが億劫になることがあります。
<真空行動>
いわゆる「大運動会」と呼ばれる、突然家の中を猛スピードで走り回る行動も、運動不足によるエネルギー過剰の表れです。
これらの行動は、軽視せず原因を探ることが大切です。放置すると体調不良につながるリスクがあります。
運動不足から生じる疾患
運動不足に陥ると、以下のような病気を引き起こす可能性があります。
<消化器疾患>
腸の動きが鈍くなることで、便秘や下痢、食欲不振といった症状が現れます。また、ストレスの影響で嘔吐を繰り返すこともあります。
<心疾患>
肥満によって心臓に大きな負荷がかかると、血液の循環が悪くなり、疲れやすさや咳、呼吸困難などの症状が見られるようになります。猫では「肥大型心筋症」と呼ばれる心筋が厚くなる疾患が多く見られ、進行すると命に関わることもあります。
<呼吸器疾患>
体重が増えることで肺が圧迫され、呼吸が浅くなったり、少しの運動で息切れしたりするようになります。慢性化すると、酸素を十分に取り込めなくなり、全身の健康に悪影響を及ぼします。
<関節疾患>
肥満によって関節や靱帯に負担がかかると、関節炎などを引き起こしやすくなります。痛みのために運動を避けるようになり、さらに体重が増えるという悪循環に陥ることもあります。
こうした疾患を防ぐためには、適度な運動とバランスの取れた食事管理が欠かせません。
室内での猫の運動促進アイデア
室内でも、以下のような工夫を取り入れると、猫にとって充実した運動環境を整えることができます。
<キャットタワー・キャットウォークを活用>
キャットタワーやキャットウォークを設置することで、室内に上下の動きが加わり、自然と体を動かせます。
<狩猟本能を刺激する遊び>
猫は本来狩りをする生き物です。そのため、猫じゃらしなどを獲物に見立て、追いかけさせたり捕まえさせたりすることでも、運動量を確保できます。
<トンネル遊び>
トンネルをくぐったり走り抜けたりする動きは、全身運動になり、ストレス解消にも効果的です。
少しの時間であっても、これらの運動を毎日続けることで十分効果が期待できます。そのため、1日10分でも良いので愛猫と遊ぶ時間を意識的に作るようにしましょう。
年齢・体型別の運動不足対策
猫の運動は「たくさんさせれば良い」というものではなく、年齢や体型、健康状態に合った方法で行うことが大切です。
<子猫の場合>
とにかく活発で、好奇心も旺盛な時期です。また、飼い主様との絆を深める時期でもあるため、トンネルやキャットタワーに猫じゃらしなどのおもちゃをプラスして、思い切り体を動かすようにしましょう。
<成猫の場合>
性格や生活スタイルに合わせた対応が大切です。人と遊ぶのが好きな子にはおもちゃを使って一緒に遊び、ひとりで過ごすのが好きな子にはキャットウォークなどで自主的に運動できる環境を整えると良いでしょう。
<シニア猫・肥満猫の場合>
関節の柔軟性が低下しているため、急な上下運動や長時間の遊びは避けましょう。短時間でも無理のない範囲で、興味を引くおもちゃを使って緩やかな運動を促すことがポイントです。また、マタタビやキャットニップなどの匂い付きのおもちゃを取り入れるなどして、少しでも興味を持ってもらえるよう工夫しましょう。
まとめ
室内で暮らす猫は、運動量が自然と少なくなりがちです。運動不足が続くと関節や心臓、呼吸器の病気、肥満など、さまざまな健康トラブルを引き起こすリスクがあります。そのため、猫の行動の変化を見逃さず、日常の中で意識的に運動の機会をつくることが大切です。
また、飼い主様と一緒に遊ぶ時間は、猫にとって運動になるだけでなく、心の安定にもつながります。猫の年齢や性格に合った方法で、無理のない範囲で継続することが、健康寿命を延ばすカギとなります。愛猫の健康を守るために、ぜひできることから始めてみてください。
なお、当院では、猫の性格やライフスタイルに合わせた運動方法や遊び方についてのアドバイスも行っております。なにか不明点や疑問などがありましたら、お気軽にご相談ください。
犬、猫、エキゾチックアニマル(ウサギ、フェレット、ハムスター、モルモットなどの四つ足で毛の生えた小型哺乳類)の診察は、『マーズペットクリニック』
神奈川県鎌倉市にある動物病院
TEL:0467-39-3882